オープンでフラットな研究文化
こんにちは。基礎生物学研究所の片岡研介です。
今、私はウィーンにある Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology (GMI) の Frédéric Berger さんの研究室に、共同研究のため滞在しています。滞在を始めてからおよそ2か月。実はこのGMI、私がポスドク時代を過ごした Institute of Molecular Biotechnology of the Austrian Academy of Sciences (IMBA) と同じ建物にあって、懐かしい気持ちもありつつ、改めてこの場所に来て感じたことを少し書いてみようと思います。

Vienna BioCenterの魅力
GMIがあるのは、ウィーン中心部から電車で15分ほどの場所にある Vienna BioCenter (VBC)。ここには、IMBAのほか、Boehringer Ingelheimが支援する Institute of Molecular Pathology (IMP)、ウィーン大学の Max Perutz Labs (MFPL)、Faculty of Life Sceineces、そしてバイオ系スタートアップまで集まっています。VBC全体では136もの研究グループ、2,000人以上の研究者が在籍していて、共通のPhDプログラムには世界80か国から約400人の学生が参加しているそうです(以前よりだいぶ大きくなっているようです)。徒歩3分圏内のキャンパスでは、毎日のようにどこかでセミナーが開かれていて、誰でも自由に参加できます。この“誰にでも開かれている”雰囲気が、VBCの一番の魅力かもしれません。こうしたオープンさとフラットな人間関係が、自然とVBC内の共同研究の多さにもつながっているように感じます。
SABミーティングという仕組み
そんなオープンなVBCは依然として健在でしたが、今回特に印象に残ったのが、GMIで先日行われた SABミーティング(Scientific Advisory Board meeting) です。GMIには現在7つの研究グループがあり、毎年秋にこのSABミーティングを開いて、研究の進捗や方向性について外部の専門家から意見をもらいます。SABのメンバーは、オーストリア外で活躍する6-8名ほどのPI。いわゆるビッグショットたち。彼らが〜3日間GMIに滞在して、各グループの発表を聞きながらディスカッションを行います。ジュニアグループには任期があるので、もちろんシビアな評価の意味もありますが、実際には「今後どう進んでいくのが良いか」を一緒に考える建設的な場として機能しています。ミーティングはGMIの全員が参加できるオープンな形式で、各ラボに45分の発表時間と30分のグループごとのディスカッション時間が与えられます。ディスカッションでは、PIだけでなく、ポスドクや学生も積極的に議論に参加します。SABメンバーも若手に質問を振ったり、意見を聞いたりしていて、まさに“全員参加型”の議論です。研究成果の評価というよりも、チーム全体としてどう良くしていくかを考える時間、という印象を受けました。
「ラボヘッド抜き」SABミーティング
さらにユニークなのは、サイエンス以外のことにも丁寧に向き合っている点です。SABミーティングでは、ラボヘッドとSABの個別面談だけでなく、ラボヘッドを抜いたSABとラボメンバーだけのミーティング が用意されています。ここでは、学生やポスドクが普段なかなかラボヘッドに言いづらいことをSABメンバーに相談できます。SABが間に入ることで、意見を上手く整理してラボヘッドに伝えることができる仕組みです。これは本当に素晴らしいと思いました。研究だけでなく、ラボ内のコミュニケーションの健全さにも気を配るSABの仕組みって、ありそうでなかなか無いですよね。
「全員で研究所を良くしていく」という文化
もちろん、すべての要望がすぐに実現するわけではありません。でも、PIや研究所の運営陣が学生やポスドクの声に耳を傾けて、より良い研究環境をつくろうとしている姿勢が伝わってきます(定期的なガス抜きともいえますが、これも必要ですよね)。学生の立場からしても、「自分たちも研究所の一員として、より良い環境を一緒に作っていくんだ」という主体性を持てる、とても良いシステムだと思いました。こうしたオープンでフラットな議論の文化が、もっといろいろな場所に広がっていくといいなと思います。
投稿者プロフィール
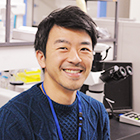
最新の投稿
 ノンドメインブログ2025.11.10オープンでフラットな研究文化
ノンドメインブログ2025.11.10オープンでフラットな研究文化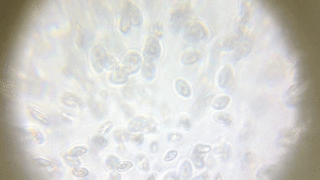 ノンドメインブログ2024.06.10テトラヒメナをみつけてみませんか?
ノンドメインブログ2024.06.10テトラヒメナをみつけてみませんか? ノンドメインブログ2023.10.08パンチ穴シールを使って顕微鏡観察
ノンドメインブログ2023.10.08パンチ穴シールを使って顕微鏡観察 ノンドメインブログ2022.08.07「余」の生物学
ノンドメインブログ2022.08.07「余」の生物学


