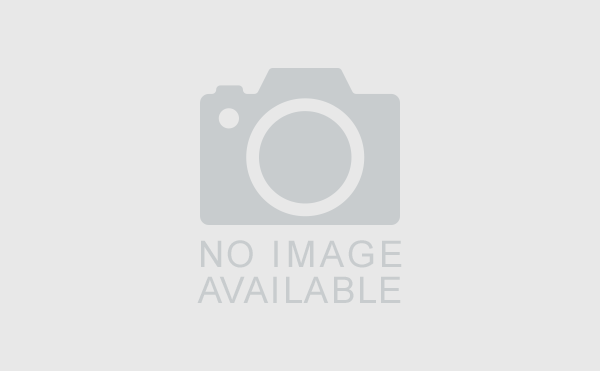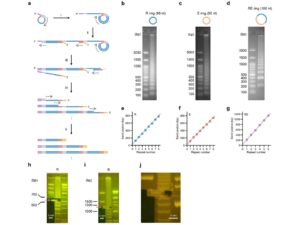平和な日々
実験をしていて何が一番好きな作業かといわれれば、修行僧のようにスライドグラスに黙々と切片をとっていくクライオスタットでの切片づくりですが、それに次いで実は結構好きなのが、ちぎったり貼ったりのコンストラクトづくり、通称サブクローニング、サブクロです。手順通りやれば必ずうまくいくはずなのになぜかハマるとハマるのがこのサブクロで、colony PCRや制限酵素のチェクでゲルの写真を撮る時は毎回ちょっとしたドキドキがあり、ずらりと思い通りの結果が出たときは、それが当然のことと分かっていても、よしっ!と小さなガッツポーズを取ってちょっぴり自分を褒めてあげたくなるのも、サブクロのいいとこです。コロニー出てきません、インサートが入っていません、インサートの長さが違います、といったお悩みはBiotechnicalフォーラムなどの分子生物学系のウェブ相談室の定番中の定番のトピックで、分子生物学覚えたての学生から百戦錬磨のプロまで気軽に参加できる話題ということもあってか、いつもなぜかやたら盛り上がっているのも微笑ましいところです。みんなやはり大好きなんですね。サブクロ。
このサブクロ、本屋でーすでおなじみのManiatisのMolecular Cloningの初版の時代から脈々と続く古典的作業ではありますが、それでも着実に技術革新が積み重ねられていて、昨今の効率の良さと手軽さには本当に驚かされます。最近、久しぶりにコンストラクト祭りを始めたのですが、まあ楽ちんなこと楽ちんなこと。短いインサートであれば、ベクターを切ったのだけ用意しておけば、あとは遺伝子合成で届いたやつを混ぜ混ぜしてやればほぼ100%の効率で入ってるし、コロニーPCRした産物を荒川さん直伝手作りAmpureで精製して外注シークエンスで配列チェックして、はい終了です。遺伝子合成でなくてPCRで断片を用意する場合でも、Taq系の酵素の正確性と速度の向上は凄まじく、PCRマシーンのスイッチ入れてプログラム入れてサンプル用意している間に機械を乗っ取られた時でも、どうせ30分そこそこで終わるんだし、まあいっか、と穏やかな気分でいられます。
全体を通してみてやはり一番大きいと思うのはligase反応がSLiCEやGibsonn Assemblyをはじめとしたseamless cloning反応に置き換わったところで、忌まわしきself ligationによるバックが全く出ない上に反応時間も短く、制限酵素を使っていた頃のSalI/XhoIやBamHI/BglIIみたいなフフフなtipsが単なる無駄な知識になってしまったのはちょっぴり寂しいですが、サブクロ周りのトラブルシュートにかける時間が激減したのは大変喜ばしいことです。seamless cloningで唯一の気がかりはその高コスト体質でしたが、Genes to Cellsに出版された京大の北畠さんの『SLiCE活性がなくなる大腸菌変異体スクリーニングで有効成分が分かっちゃいました論文』のお陰で、完全解決しました。ちなみに北畠さんのオリジナル論文では手作りのバッファーで最適条件を探しておられていますが、自分で試薬も作れない最近の若者がすくすく育っておっさんになってしまった僕は、NEB付属のバッファーでやっていて、普通にうまく行ってます。知る人ぞ知る、通称Kitabatake Solutionのレシペは以下のとおりです。まず2x bufferを作って、それで薄めたExoIIIと(ExoIIIはほんのちょっとしか使わない)、ExoTを混ぜるだけです。
1. 2x bufferを作る
Glycerol: 1 mL
NEB 10xBSA (10 mg/mL): 840 µL
NEB buffer 4: 160 µL
2. Exo III (NEB M0265S)を2x bufferで100倍に薄める
3. 2x buffer 1600 uLに薄めたExoIIIを2 µL、ExoT (NEB 2170A)を50 µL加える
これで出来た2x Kitabatake Solutionは-20ºCで数年持ちます。これを2 µL、ベクター(10 ngぐらい)1 µL、インサート1 µL(ベクター等モルぐらい)を混ぜて37ºC 5 min、65ºC 5 minではい出来上がり。AmpのときはSOBのprecultureもしてませんが、拾いきれない数のコロニーが出てきて、そのうち2つぐらい拾えば十分な感じ。そしてコロニーPCRして、ちょとドキドキして、小さなガッツポーズ。かつてプロジェクトの律速段階になりかねなかったサブクロは、のぞみに乗ったときの静岡県ぐらい、あっという間に通過してしまう簡単プロセスになりました。というわけで、ルンルン気分で仕事を進めていたのですが、、、
好事魔多し。
サブクロが終わったあとはおなじみmidiprepなわけですが、ここ最近、思いもかけないトラブルが出来したのです。コロニーPCRであたりだったコロニーを、つつき直して一晩。さてキアゲンでもするかと翌朝インキュベーターを開けてみると、、、
あれ?増えてない。6個コロニー拾ったのに、一つだけ全く透明で、増えてません。あれ?コロニー拾いそこねたかな、ということで(そんなはずない)、もう一度拾い直したら、翌日は増えてたので、まあ、そんなこともあるかと思っていたのですが、
翌週4つ拾ったら、また一本増えてません。んー、なんかおかしい。
miniprepでは普通に増えます。これ、前培養が必要なのかな。そんなはずない、と思いつつ、ラボのハマりはありとあらゆる伝説が生まれる場です。前培養すべし。ここでまた一つのトリビアならぬmidiprepまわりの伝説が生まれようとしたわけですが、その増えた溶液を200 mLのコルベンにいれた40 mLのLBに入れたところ、翌朝きれいな透明な液。透明な液。ん?なんだこのカスは。これ溶菌している!院生時代にlambda gt10のライブラリのスクリーニングをしていた頃以来、20ン年ぶりに見た溶菌です。だれもファージなんて使ってないのに。どこからコンタミ??
そういえば、学生時代を過ごしたラボで、廊下に並んでいた2台の大型シェーカーのうち、普段使われていないシェーカーを使うと溶菌するというトラブルに見舞われたことがありました。ああ、あのシェーカーね、呪いがかけられているからね、使わないほうが良いよ、というような分かったような分からないような説明を受けたような気もしますが、んなわけあるか、と禁断の扉を開けて構わず使ったところ、見事トラップに引っかかってしまったわけです。当時はファージを使っている人もたくさんいましたから、誰か溶菌したコルベンぶちまけたのかな、と思い、アルミキャップを被せたガラスの試験管でなくてディスポの試験管につついてきちんと蓋を閉めたらそのトラブルは解決したので、その時は
「ふた、しっかり閉めるべし。アルミ、きっちり被せるべし。」
という、midiprepまわり、その8、ぐらいの伝説が生まれたのですが、その後20年以上こんなトラブルなかったので、すっかり忘れておりました。そうだったそうだった。伝説、大事だよね。信じる者は救われる、ということでガチガチにアルミを被せてパラフィルムでシールまでしたのですが、、、
4本中2本増えない。むしろだんだんひどくなっている。
これ、コルベンが悪いんかなあ、と、疑い始めたら登場人物全てが疑わしく思えてきます。名探偵コナン状態。トラブルが続くと、だんだん正しい判断ができなくなってきます。このコルベン、だめ、というテープを張って、オートクレーブしたそのコルベンにLBを入れて培養したら増えないなんて事があったりすると、オートクレーブしても死なないファージに取り憑かれた呪のコルベン、なんていう伝説が生まれそうです。ああ、あのコルベン呪われているからね。塩でも撒こうか。
そういえば昔読んだ愛読書、我が北大が舞台の動物のお医者さんでも、E. coli = コリー =ラッシーちゃんを進撃の巨人が如くなぎ倒す、なぜか巨大なキューピーとなったファージが出てくるこんなシーンが有りました(第17話)。

「大腸菌なんで今どきプールにも食べ物にもあふれているというのに〜」という謎の院生菱沼さんの叫びがチャーミングですが、当時はこれは漫画の中の世界だけだと思っていました。まさか30年あまりを経て自分の身に降り掛かってくるとは。オートクレーブしても死なないファージなんてあるわけないし、冷静になって考えれば、大元のLBの培地にファージがコンタミしたんだろう、というのが、妥当な判断です。今度はLB培地をいれたコルベンごとオートクレーブして、Ampを足して、コロニーつついて、翌朝。
4つつついたのが4つとも増えてない。
症状はどんどん悪化していきます。もう末期症状、といっても良いかもしれません。いつのまにやら後ろから次々やって来るシークエンスチェック済みのコンストラクトが、大渋滞の列を作ってます。あーなんとかせんといかん。でも一体どこにファージが??やはりオートクレーブしても死なない新型ファージ爆誕?残る可能性はAmpぐらいですが、僕のラボではAmpは70%のEtOHに溶かしています。こうしておけば-20ºCでも凍らないのですぐ使えるし、バクテリアのコンタミもないし、当然ファージのコンタミもないはず。
ン?待てよ。AAVは70% EtOHでは死なないからブリーチでdecontaminationするし、ノロウイルスもエタノール消毒出来ないし、ファージもよくよく考えたらmembrane持ってるわけではないのでEtOHが効かない??というわけで、Ampを作り直して渋滞しまくっていたコロニーを拾ったところ、

やったーっ!全部増えた!つついた大腸菌が増えるというのがこんなに嬉しいことだったとは!当たり前の日常が当たり前でなくなる時、人々はほんとうの幸せの意味を知るとはこのことなのか。ああ、愛しの大腸菌よ。ということで、ここ2,3ヶ月苦しまされてきた憎きAmpをオートクレーブ送りにし、この菱沼さん再現事件はめでたく解決の運びとなりました。最初のコンタミがなんだったのか、なぜファージを使ったことのないラボで溶菌騒ぎが起きたのか、未だにその原因はわかりません。北の大地にはファージが多いのかもしれませんが、そもそもファージの研究は自然界にあるものを、あれ、これなんだろうと不思議に思って拾ってきたところから始まったものでしょうし、謎の溶菌事件をきっかけに、これなんのファージだったんだろうと調べたくなる気持ちもちょっぴり。このファージの配列を大腸菌のCRIPSRアレイに入れとけばファージ耐性のコンピテントセル作れたりするのかなとか、やってみようかな、とか、油断しているとどんどん研究が横道にそれてしまいそうですが、ああでもないこうでもないと大騒ぎして、なんだか学生時代に戻ったような、若返ったような気分の、この2,3ヶ月でした。
たかがサブクロ。されどサブクロ。うまく行ったりいかなかったりの研究のこんな日常も、結構楽しいものです。この平和な日常がいつまでも続きますように
投稿者プロフィール

最新の投稿
 ノンドメインブログ2025.06.27来し方行末~パート1
ノンドメインブログ2025.06.27来し方行末~パート1 ノンドメインブログ2025.02.11平和な日々
ノンドメインブログ2025.02.11平和な日々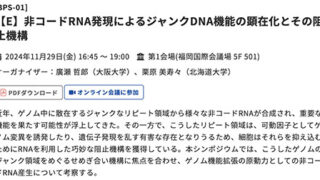 ノンドメインブログ2024.11.25MBSJ2024のシンポジウムのすごいゲスト
ノンドメインブログ2024.11.25MBSJ2024のシンポジウムのすごいゲスト ノンドメインブログ2024.09.17奇遇癖
ノンドメインブログ2024.09.17奇遇癖