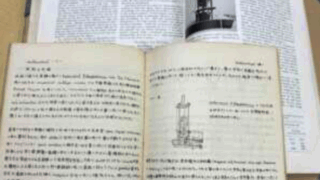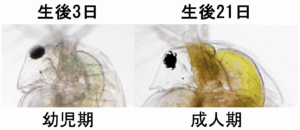論文の読み方
 (写真上はGregory et al, Plant Physiology, 29, 220-229, 1954)
(写真上はGregory et al, Plant Physiology, 29, 220-229, 1954)
私の父は中学校の理科・生物の先生でした。生きていれば今年94歳。理学部卒で、家ではほとんどなにも語らなかったので、何を考えているのかさっぱりわかりませんでした。亡くなる少し前のこと、「これをあげるよ」と言われて、古いノートをもらいました。中を見てびっくり?! 父が新米教師の頃、雑誌Plant Physiology 1冊まるまるを日本語訳にして書きつけたものでした(写真は、Gregory et al, Plant Physiology, 29, 220-229, 1954)。タイトルからディスカションまでを全て和訳し、図や表まで手書きで写しています。戦後10年頃のことです。
いろいろな思いが交錯しました。まず美しい。辞書を引きながら長い時間をかけて和訳したのでしょう。万年筆で書かれた文字は達筆ではないけれど、整然としていて少し誇らしげです。ページの間から感じられる若き父の気配が感じられます。また、今の時代の学校の先生、あるいは万人にないであろう時間の余裕や思いの豊かさを感じました。豊かさといえば、うちは裕福でなかったのに、このジャーナルは家で個人輸入していたそうで、当時は船便で届いたそうです。まあそうでもしなければ、コピー機もない時代、一冊のジャーナルを誰かと共有しながらここまでじっくりと読むことはできなかったかもなあ、と想像します。他の雑誌などはどうやって読まれていたのでしょう?まあそれはおいておいて、新米の先生なら他にもっと重要なするべきことがあったのでは?なんて、娘としてちょっと意地悪な気持ちも湧きました。でも、父にとって誇り高き独身時代の楽しみを、できの悪い娘の私に手渡してくれたことは光栄で、宝物になりました。
さて、ときは過ぎて私が論文を読めるようになったのは、Johns Hopkins大学の大学院生のときで、Bill Earnshaw先生の研究室でのジャーナルクラブのおかげと思います。ここでは、ラボメンバー全員が事前に当該論文を読んでくることが義務でした。発表担当者は、背景をさらっと説明するだけで、そこから先は司会者になります。そしてFigure毎に誰かを当てます。指名された人は実験の目的や方法を簡単に説明します。みなさん読んでくること前提なのでそこには時間を使いません。その後、データとその解釈を簡単に説明して議論に移ります。ここからが本番です。オーサーが主張していることはこのデータで証明できるか?実験のデザインに不備はないか?要旨は言い過ぎてないか?本来ならどういった実験をどのような実験材料で行うべきか、などを全員参加で議論させられます。”Results”に書かれていることをそのままなぞるなんてもってのほかで、集中砲火をあびます。その解釈でよいと思っているのか?あなたは同意するのか?ここの論点に疑問を抱かないつもりか?など責め立てられます(笑)。議論は客観的で、「このオーサーだったら言いかねないね」とか、「なんとなくおかしいね」などの主観的な批判はシャットアウトです。目の前にあるデータのみに基づいた具体的な議論をします。
こうして、論文を批判的に読むと理解しやすい、ということを体感しました。ディスカッションを通して、ああ、自分が疑問に思っていたことはまわりも同様に感じていたんだ、私が無知だからでも英語ができないからでもなかったんだ、という安堵を覚えることもありました。時にgood questionなどと言われて嬉しくなったこともありました。
このかたちのジャーナルクラブを映画鑑賞に例えると、既に映画を見た者同士が感じたことを熱く語りあう感じ。それまでのジャーナルクラブは、映画を見ていないひとにストーリーを一から紹介する感じです。前者は間違いなく私に必要な経験でした。
最後に、遠い将来の論文はどうなるのでしょうか。AIの役割は拡張し続け、論文を書くのも読むのも査読者の選定も査読もエディターのディシジョンもすべてAIでする、そんな独立循環ができるのでは?と推察し、それはそれで楽しみです。でもそれとは別に、ヒトの脳みそを通過して作成された論文、というのがとても貴重になるかもしれない、という予測はどうでしょう。ハンドメイドクッキーならぬハンドメイド論文。「添加物は一切使っていません」ではなく、「AIは一切使っていません」が売り物。そして読み手もAIは使わない。効率は悪いけれど思いもよらぬ環境ができるかもしれないですね。