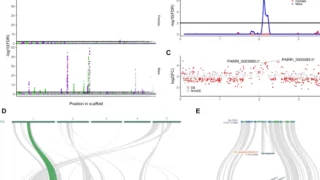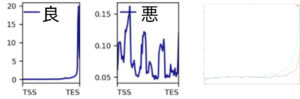国際クマムシ学会開催!
先月6月23-27日に、慶應義塾大学先端生命科学研究所(山形県鶴岡市)において、クマムシ研究の国際学会 16th International Symposium on Tardigrada (https://tardigrada.iab.keio.ac.jp) が開催された。17カ国から120名の参加者があり、おかげさまで盛況のうちに幕を閉じた。国際クマムシ学会は1974年から続く3年に1回開催の歴史ある学会だが、ヨーロッパ・アメリカ以外での開催は初となる。日本のクマムシ研究における国際的なプレゼンスが今回の誘致に繋がったと言えよう。おかげさまで本会には本領域、学術変革領域研究(A) 非ドメイン型バイオポリマーの生物学からも補助をいただいた。

図1. 会場のフォトブースの様子。おかげさまで、本領域にスポンサーいただいた。
学術プログラムは、形態学・生態学・分子生物学・ゲノミクスなど多岐にわたり、4名のキーノートスピーカーによる基調講演に続いて、57件の口頭発表と61件のポスター発表が行われた。基調講演では、クマムシを含む脱皮動物の系統的位置づけから乾眠メカニズム、細胞保存への応用、さらに比較的近縁な線虫における発生研究の最先端技術に至るまで最前線の知見が紹介され、口頭・ポスターの各セッションでも最新のオミクス解析や遺伝子編集技術を活用した研究成果が報告された。質疑応答は連日予定時間を超えるほど活発で、若手研究者が登壇するポスターセッションでは先端的なアイデアが飛び交い、共同研究に向けた新たな連携が多数芽生えた。
国際クマムシ学会の参加者は21世紀に入って順調に増加を続けており、特に分子生物学研究の割合が大きく増えている。今回も半数弱のセッションが分子生物学や生理学的研究で占められ、我が国が牽引してきたクマムシのゲノム・分子生物学研究が着実に分野に大きく貢献し広がってきた手応えを感じた。本学会では初めての試みとして、学会に先立った21-22日にチュートリアルセッションを開催し、そこで本学術変革領域で開発したクマムシin vivoでの遺伝子発現系TardiVecのチュートリアルなども行い、こちらも大変好評であった。
研究発表だけでなく、開催地・鶴岡市の文化や歴史に触れる特別プログラムも大きな特色となった。出羽三山神社での参拝と精進料理体験を含むエクスカーションでは、地元の羽黒高等学校国際コースの生徒たちが英語ガイドを担当し、海外参加者との交流を通じて生徒自身にとっても貴重な国際経験の場となった。さらに、致道博物館や旧風間邸を巡るシティーツアーでは、庄内藩の歴史や町屋文化、発酵をはじめとする食文化が紹介され、参加者は地域の自然と伝統を五感で堪能した。こうした取り組みに対し、「学会を通じて地域全体の温かさと魅力を感じた」との声が多く寄せられ、学術イベントが地域振興にも寄与したことがうかがえる。

図2. 学会集合写真
本シンポジウムは、学術的な成果と地域連携の双方で大きな成功を収めた。世界各地から集った研究者が最先端の知見を共有し、今後の共同研究の基盤を築くとともに、鶴岡の歴史・文化・自然を深く体験することで、研究と地域が相乗的に価値を高めるモデルケースとなった。本学術変革領域の国際的プレゼンスの高さを再確認すると共に、クマムシ研究の国際拠点形成を視野に入れ、継続的な研究と交流の拡大を図ることが期待される。
投稿者プロフィール